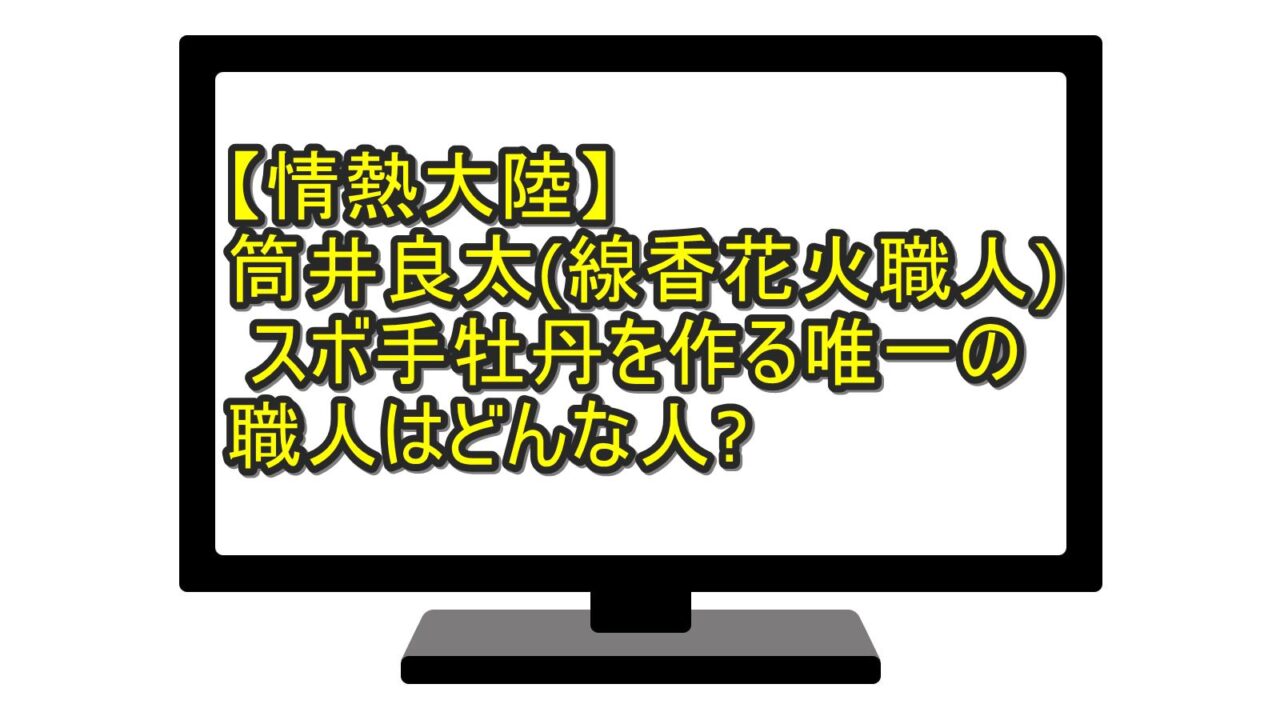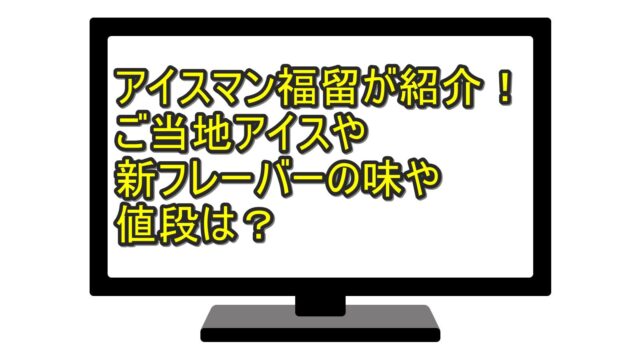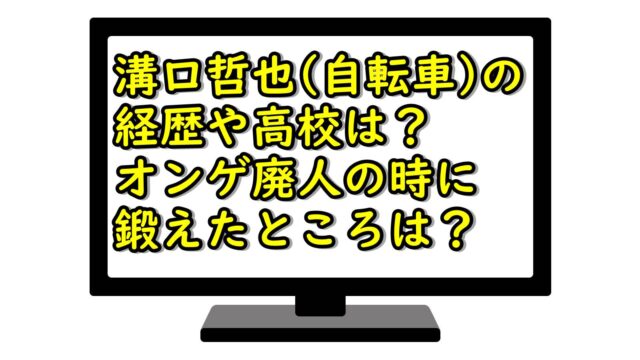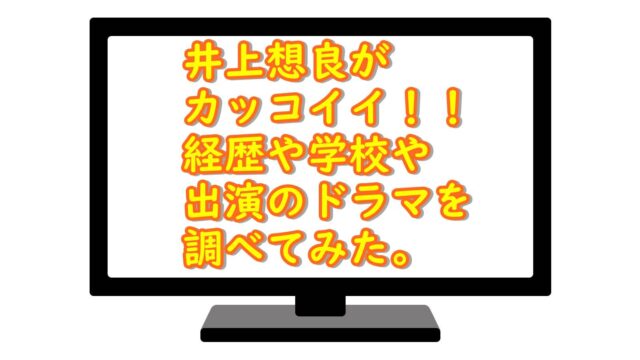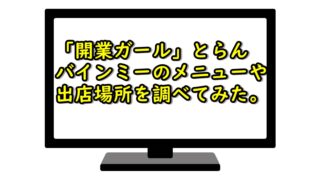こんにちわ。keiです。
8月にも入り、花火のシーズンになってきましたね!
ここ数年は、コロナの影響で花火大会が中止にところが多く、恒例の花火大会に行けなくて残念な状況です。夏の風物詩が消えていくのは寂しいものですね。
8月15日の情熱大陸では、線香花火職人の筒井良太さんの特集が組まれています。
線香花火は、その淡く儚い輝きから大人から子供までみんな大好きな花火ですよね。
そんな線香花火を作る筒井良太さんがどんな方なのか調べてみましたので紹介したいと思います。
目次
プロフィール
戦国時代の筑後の火薬方、筒井一族のルーツをお持ちの方です。
1973年生まれ。福岡県出身。
もともと親御さんが花火職人の方だったようで、子供の頃は職場が遊び場だったようで実験などが大好きだった様子です。
高校卒業後は、すぐに家業を引き継がずに、愛知県の自動車製造会社に就職しています。
就職から3年後、八女の花火製造所「隈本火工」に修行に入ります。
それから3年たった1995年に3代目として家業を継がれました。
そして2011年3代目 筒井時正を襲名されています。
結婚は、妻の今日子さんに出会い24歳の時にされていて、4人(3男1女)のお子さんに恵まれています。
筒井時正玩具花火製造所の場所はどこ?
場所は、福岡県みやま市高田町竹飯(たかたまちたけい)1950-1です。
熊本との県境に位置する町なので、福岡からも熊本からも行きやすい場所ですね。
スボ手牡丹という線香花火はどんな花火?
線香花火には、「スボ手牡丹」と「長手牡丹」があります。
違いは、火薬を包む素材。藁で包むのか、紙で包むのかの違いだそうです。
長手牡丹の線香花火とは?
「長手牡丹」は火薬を包む材料が紙で出来ています。もともと関東地方を中心に親しまれていた線香花火で、我々がよく目にするのは、「長手牡丹」の線香花火の方が多いです。
もともと、関東地方では、米作りがすくなく火薬を包む藁を供給できないことから、紙に変更されました。現在は、輸入品も始め、「長手牡丹」の線香花火が主流です。
スボ手牡丹の線香花火とは?
「スボ手牡丹」はワラスボの先に火薬をつけて作る線香花火です。米作りが豊富だった西日本中心に親しまれていた線香花火です。
線香花火は、「スボ手牡丹」の形が原型とされており、約400年も前から続いています。
今では、国内生産をするところがなく、筒井時正玩具花火製造所で唯一作られているそうです。
「スボ手牡丹」と「長手牡丹」の持ち方や特徴は?
持ち手の強度が違うため、スボ手牡丹と長手牡丹では持ち方が変わります。
藁で作られた「スボ手牡丹」は、上斜め45度で持ち、紙で作られた「長手牡丹」は、下斜め45度で持つと良いそうですが、「スボ手牡丹」の場合は、上向きで持つと花火が風で自分の方に来てしまうこともあるようなので、立てて持つ場合は、何かに刺して花火を楽しむのがいいでしょう。もちろん、スボ手牡丹の線香花火でも下向きで花火を楽しむこともできます。
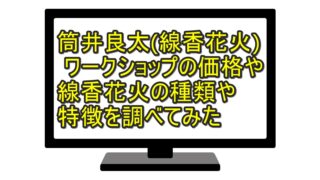
まとめ
いかがだったでしょうか?夏の風物詩を代表する花火職人を少しでも紹介できていればと思います。自分も線香花火は、長手牡丹の線香花火しかしたことがなかったので、機会があれば、スボ手牡丹の線香花火もやってみたいと思います。